| 【3】どんな「気付き」が「得られる」? 〔A〕他者の情報を受け取る難しさ で,講演のサブタイトル「制作体験で得られる気付き」ですが,では実際にどんな気づきが得られるのかということを考えていきましょう。 お手元の記事資料を読んでください。(毎日新聞02.08.22の記事) 新聞記事を読まれたら,以下に記入してください。 塩釜港女子高生死体遺棄事件の受け止め方 ①新聞記事を見て… 犯人は( )(その可能性 %) (①への書きこみが終了した後) 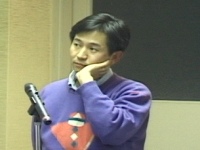 次に,この新聞記事の2日後に今TBSで放送しています「サタデーずばっと」という番組で私がしたリポートを御覧いただきます。全く違った情報の発信の仕方をしております。 次に,この新聞記事の2日後に今TBSで放送しています「サタデーずばっと」という番組で私がしたリポートを御覧いただきます。全く違った情報の発信の仕方をしております。(VTR視聴 約12分) では,この段階でプリントの②に書き込んでください。 ②下村リポートを見て… 犯人は( )(その可能性 %) 犯人はだれ?その可能性は何%? 新聞記事を見て犯人は菅原と書いた方,挙手を。(→1人を除き全員が挙手) では,菅原以外のことを書いた方は?何とお書きになりましたか? (会場)「分からない」と書きました。 あっそうですか。では皆さん,「可能性」の数字は何と書きましたか? 100% 十数名,80%以上 約半数,50%以上 少数,50%未満 少数 では下村リポートを見て 犯人は菅原と書いた方?……3分の2くらいですね。菅原以外のことを書いた方?何と書かれましたか? (会場)「菅原の友人」と書きました。 ほぉー。では皆さん,「可能性」の数字の方は? 100% ゼロ,80%以上 4人,50%以上 過半数,50%未満 1割程度 まあこんな感じでですね,どういう情報に接するかで簡単に印象って変わるわけです。この事件に関して結局今どうなっているかは,あえて申し上げません。結果がどうであれ,「容疑で逮捕されている」というだけの時点で我々がどう情報を受け止めればよいか,白か黒かで結果論としてどうこう言うべきではありません。松本サリン事件の河野さんも《結果的に犯人ではなかったから》あのときの報道はひどいじゃないか,ではなくて,《結果的にどうであろうと》あの時点で河野さんと決めつけたメディアもひどいし,それをそのまま信じた日本社会全体も間違っていたというわけです。 このように他の人から情報を受け取るということは非常に難しいことなのです。スーッとこういう新聞記事を見ると,ああ菅原っていうのがやったな,ということになるけど,よくよく分析してみると何も確たることはないじゃないか,ということになるわけです。ですから結局鵜呑みにしてはいけないんだ,ということを自覚するかどうかなんです。 |
| 講演記録トップページへ 前へもどる 次へすすむ |